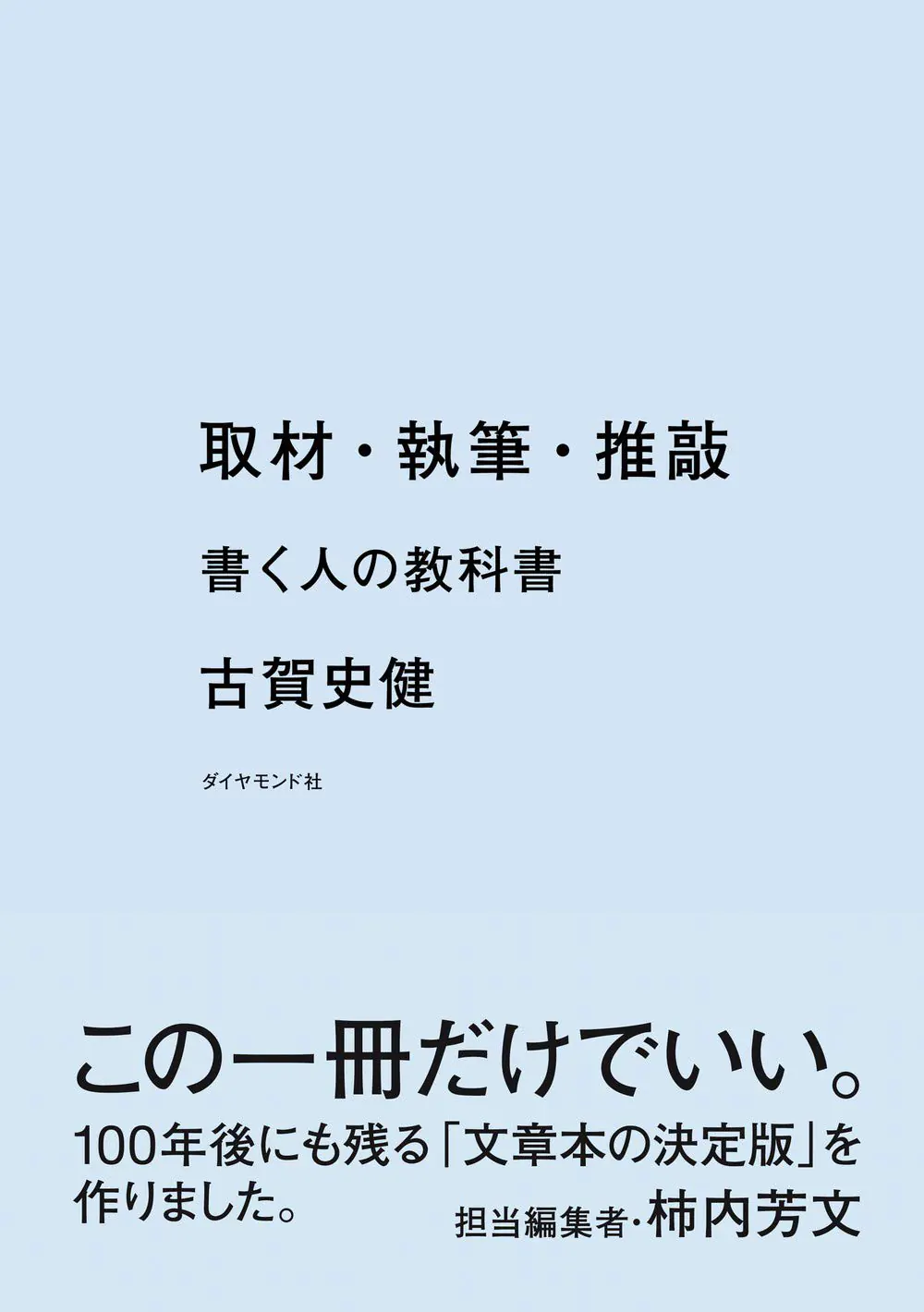bravesoftの
プロフェッショナル社員
社員紹介 Vol.16 古泉 功

古泉の履歴書
 人生の大半でプロジェクトマネジメントに携わり生きた知見をもった存在
人生の大半でプロジェクトマネジメントに携わり生きた知見をもった存在
- 1963年12月 新潟県新潟市にて生誕
- 1975年1月 群馬県高崎市に引っ越し
- 1979年4月 群馬県立前橋工業高校に入学
- 1982年4月 沖ファームウェアシステムズ入社
- 1987年1月 東京に上京し、フリーランスプログラマーを開始
- 1996年4月 インクリメントP株式会社(現:ジオテクノロジーズ株式会社)入社
- 2021年1月 bravesoft入社、 パートナープロダクト部門に配属
- 2021年7月 QMOリーダーとして、QMSystemの運用を本格開始
- 2022年1月 2021年下期のBest Project Award受賞
 古泉の流儀
古泉の流儀
はじめに
bravesoftは2021年8月よりQMO(Quality Management Office:組織的な品質管理活動)を実現すべく、「QMSystem(Quality Management System)」の稼働を開始した。
組織的な品質管理を実現するシステム——QMSystemとは一見難しく聞こえるが、大きく実現したいポイントは「品質の水準を守ること」と、「社員の能力水準を向上させること」の2点となる。
背景として、これまでbravesoftは多くのサービスを世の中に提供してきたが、その中で古株であったり、スキルの高いディレクターやエンジニアの知見が属人化し、「○○さんであれば知っている」「○○さんしか対応できない」という状況が顕著となっており、極論そのような担当がアサインされた案件は順調にプロジェクトが進行しているのだが、そうでない担当がアサインされた案件では安定せず稀に炎上するケースがあること、パートナープロダクトへの取り組み姿勢やプロジェクト進行方法・プロセス設計に対して、事業統括する青木取締役CDOは危機感を覚え、事業思想やプロセス自体をDXしたいと考えていた。
熟考の末、「最新・最善のプロジェクトに関する知識・ノウハウを資産化・共有化し、誰もが最適解を使える状況」を作り出することが重要であると青木は考えた。
これにより、経験の浅いディレクターやエンジニアが常に最適解を持ち、品質の向上を実現することができると共に、個人個人のスキル向上も実現できることが理想であると考えたが、「言うは易し、行うは難し」であるのが悩みであった。
このような仕組み化を熟知し、管理できる人間は当時のbravesoftに存在しなかったのである。
そのような最中、個人としてこれまで多くのプロジェクトを経験し、そうした品質管理の仕組み化に対する知見をもった男であり、今回プロフェッショナル社員として紹介する古泉が、長年勤めていた会社を退職し、転職活動を行う上でbravesoftの存在を知り、関心を持ち、選考面談に来た。
そこで初めて青木と古泉は出会い、青木の実現したい世界は古泉の参画により、仕組み化(QMSystem)をすることで実現できると思い、古泉に夢を託すことになったのである。
本記事では古泉のこれまでの経歴と、古泉がこれまで行ってきたQMSystemの事例、更には古泉が考える未来へのビジョンについて紹介させていただく。

入社初日の2021年元旦に掲げた書初めの文字は初心から始める「一」
紙でプログラミングをしていた新卒時代
1963年12月、新潟県新潟市にて古泉は生を受けた。
元気に育った古泉は近所の「ガキ大将」で、少年時代は毎日ヤンチャをして遊んでいた。
そして父の仕事の都合で、小学5年生の冬に新潟から群馬県の高崎市に突然引越した。
さよならも告げずに友達と離れたのは寂しかった。その中には今の古泉の奥様もおり、楽しく生まれ育った新潟を離れたことに苦悩したものの、群馬での新生活が始まり新しい友人ができて、徐々にその寂しさも癒えていったのだが、またも中学で父の仕事の都合で高崎から前橋へと引越し、転校生いじめにもあったが大暴れして跳ね除け、新たな友人も作り多感な小学校〜中学校時代を過ごした。
高校は群馬県立前橋工業高等学校に進学。
少し先輩に群馬の有名人BOØWYがいた時代、暴走族や校内暴力を身近に感じていた時期ではあったが、古泉はそうした中で中立な立場をとり、どちらとも仲良く帰宅部活動や勉学に勤しみ、成績は良かった。
父親により理不尽な環境を強いられたので非行に走る理由は幾つもあったが、そうすると父に負けた気がするのでそうはならないよう意識していた。
成績は良かったので卒業後は日大の推薦枠をもらい話を進めていたが、またも父の事情で就職することを余儀なく選択せざるを得なくなり、地元で最大手企業の一つである沖電気が初のソフトウェア専業子会社「沖ファームウェアシステムズ」を作るということでそちらへの就職を決めるに至った。
この時の選択が、古泉の人生において重要な決断であったのは言うまでもないだろう。
そのような形で就職を決めた古泉であったが、父から独立することが最優先で将来性あるソフトウェアを選んだものの、高校時代のプログラミング授業は「性格的に苦手な仕事」と捉えていた。
しかしながら沖電気が銀行や郵便局を顧客として養ってきた設計ノウハウ、3ヶ月にわたる手厚い研修、20数名の同期でのグループワークを通じて得た結束、優しく厳しい先輩達、これからはコンピュータのプログラミング人材が大切であり育てたいという期待の中で、否応なく力をつけていった。
古泉が担当したのは銀行ATM端末の通帳を扱う自動支払い機のファームウェア。
通帳記帳機には、CCDセンサ・磁気ストライプ・プリンタ・ローラーなど様々な制御要素が含まれており、そこで機械制御のあらゆる要素を吸収することが出来たのは非常に幸運であった。
ここで担当した業務は、アセンブラ言語を使用していた。256種類あるマシン語は全て暗記していたが、それは特殊な事ではなくパッチによるデバッグで自然と覚えた結果であった。
当時はまだパソコンが無かった時代。2進数入力用スイッチがズラッと並んだボックスにアドレス・コードを打ち込んでデバッグしていた。
今では考えられないが、手書きでコーディングもドキュメンテーションも行っていた時代である。
「コーディングシートという紙にコード書いて、それをパンチャーという担当者に渡し穿孔紙テープになって出てきたのを大型コンピューターに読み込ませるのが当時のプログラミングでしたね。」
今では考えられない環境であるが、古泉が22歳までの4年間この会社で働く中で、この1982年から1986年という4年間で時代は大きく進化していった。
すぐに緑色の英数字しか表示できないエディター機能が搭載された今のPCに似たアセンブルマシンが登場し、やがてUNIXも誕生、そして沖電気もif-800というパソコンを出し、少しずつパーソナルコンピューターへの移行が行われつつあった中、ITの黎明期に今では考えられない業務量で、残業も繰り返して古泉は鍛練を重ねていた。
「先輩の書いたコードをひたすらフローチャート化することで読解力を養い、C言語からHCPチャートで構造化プログラミングに取り組むことで分析設計力が磨かれたと思います。銀行向けのお堅いドキュメントもひたすら書きました。ある意味、型にはめられたのですが、今考えるとそれが良かったのかもしれません。“どうしてこのようなことを書く必要があるのか?”などの意味を考えながら、ショートカットも回り道もせずに仕事してました。守破離の守を高ストレスでこなすことを強いられたのですが、意味を考えながらこなすことで巨人の肩に乗れ、破離へ繋がる反発エネルギーが養えてその後の成長に繋がっていたように今考えれば思えます」
急成長時代なので仕事は山ほどあり、そして地方では皆が車通勤なので終電で帰るという制約はない。
疲労困憊で帰宅し、シャワーを浴びてまた出社するなんてことも多かった。
しかしながら、まだ昼と夜の区別がつく古泉はまだ恵まれており、同期で高機密を扱う社員は窓もない部屋に24時間缶詰になって働き、会う度に痩せていた。
技術が劇的に進化する、そのような時代だった。
そしてこの頃、忘れられないエピソードがある。
当時は今のようにデータのバックアップが十分に取られておらず、更にはデータも簡単に消去できてしまう保護体制だったため、プロジェクトのデータを誤って全消去してしまったことがあった。
「法廷みたいなところに立たされ、周囲から徹底的に“なぜなぜ分析”を詰められました(笑)ただ、今考えるとそれを経験したから品質に関する意識が向上したとも思えます」
当時、デバッグコードを仕込むなんて概念もない時代に、プログラム暴走を解析しやすい痕跡を残すコードを仕込んでいたので途中までの復元は行え、事なきを得ることができたが、この時代にこのようなことをやっていたのは恐らく古泉だけだったであろうと当時を振り返る。
実務を通して、「リスク回避」含むプロジェクト管理の方法論が萌芽しつつあった。
そして、社会人としての基礎を沖ファームウェアシステムズで学んだ古泉は、より大きなことを実現するために、同期と2人で会社を辞め東京で自立することを決める。
古泉が22歳の春だった。

社内メンバーにQMOやアセットの活かし方について語りあう勉強会も定期的に開催
“社長が一番稼ぐ会社ではなく、社員が稼ぐ会社”を目指して
そうして東京に上京した古泉は、個人事業主として生計を立てる道を選んだ。
会社を辞める時、周りの先輩には「甘くない、潰しが効かない」と散々脅されたのだが、これまでの4年間で「アセンブラ」「C言語」を学んだ経験と、お堅い銀行系の仕事で得た品質をプロセスで作り込む経験、回路設計も経験していた事が功を奏し、仕事でなんら悩むことはなかった。
形だけ覚えていたのではなく意味を考えて仕事してきたのが功を奏した。
個人事業主としての業務は、これまでの4年間に比べれば楽ですらあった。
仕事先でこれまでに得たノウハウを応用・アレンジして教えることが多く、それでいてこれまでに経験しなかった業界の仕事を積極的に選び新しいことを覚えるのがとても楽しかった。
C言語とアセンブラはコンパイラを自分でも作れるほどの技量を身につけていたので、新しい言語を覚えるのも楽であり、物申す業務委託は、現場を改善し信頼と報酬をうなぎのぼりに得ていった。
これまでの倍以上の稼ぎをしている古泉達を追いかけて地元の同僚達も数名加わり、チームで業務を受けることも多くなり、プロジェクトチームのマネジメントも20代半ばで行うようになっていた。
そうしてその延長線上で起業の話が舞い込んだ。
当時お世話になっていた企業の役員から「出資するから君達優秀なフリーランスで会社を作らないか」と誘いを受け、古泉を社長とした優秀なフリーランス集団で会社を作ろうと準備をしていたのが90年前後、この後、日本中の経済を狂わせる“悪夢”の到来を前にした絶頂期であった。
「“トップが一番儲かる仕組みはオカシイ“、“社員が社長より稼いで良い会社”を作ろうと色々準備していたんですが、バブル崩壊の影響で起業はダメになってしまいました」
起業計画の合宿をしていた矢先のバブル崩壊で、明日の仕事も心配な状況になって起業の夢が途絶えてしまった古泉であったが、前述の通りの理想の企業というビジョンは変わらずに持ち続けていた。
そんな最中、古泉の以前の仕事ぶりを人伝に知った方から正社員で働かないかという打診を受ける。
古泉が上京し、フリーランスを始めてから10年が経った1996年の頃だった。
断るつもりで話をしにいった古泉であったが、そこで待っていた社長は古泉が語ったビジョンを一頻り聴いた後「私もそのような会社を作ろうと思っていたんだよ。親会社には内緒だけどこの社名は親会社を越えたいという意味も込めてつけたんだ」と聞き意気投合、まさかの展開で入社することを決意したのだった。
「ちょうど少し前にカーナビの仕事をしたのもあり、電子地図には個人的に注目していました。リアルとサイバー空間を繋ぐ鍵になると思っていたし、今でいう“Google Map”もまさにそうですよね」
そして古泉は1996年にインクリメントP株式会社(現:ジオテクノロジーズ株式会社)に入社。
入社後は社の看板PCアプリ「MapFan」の開発チームに配属、早々にリーダーからマネージャーに昇格して開発チームを管掌、さらに利用シーン拡大のため社外製品との連携提案に奔走することとなる。
古泉がインクリメントPに入社した1996年からの90年代後半は、Microsoft Windows 95やインターネットの普及とともに全世界がIT時代に突入した時期でもあった。
幕張メッセでは、ITの大イベントが年に何度も行われ、そこでは携帯電話が無償で配られ、家庭にもPCが急速に普及し始めたこの時代。
イベントに立って開発者が直接エンドユーザーの要望を聞くことでエネルギーをもらい、求められることとやるべきことがたくさん見えて毎日業務に追われていたが要望を一つ一つ叶えていくことにやりがいがあり幸せであった。自社製品開発を通じて“マーケティング要素”が加わり、社会との繋がりを実感できるようになったことで、20代の受託開発では味わえないプロダクトグロースに、エンジニアとして二段目のロケットとなる成長の場を感じた。
その一方、担当範囲も変わり複数パッケージソフトや受託開発も取りまとめていたが、複数プロジェクトを1人でマネジメントすることには限界があった。
「世の中にはまだPMO(Project Management Office)の考え方はありませんでしたが、必要に駆られて似たような仕組みを作ったのです。私一人がPMで、お客様とプロジェクト計画から要件定義、つまりゴールまでを定義します。プロジェクトにおいて私は全てのルールを決められる神というとちょっと違うか、責任感で言えば執刀医と同じで、“プロジェクトを通じて社会を良くする”プライドがPMの社会的地位を向上させるんだ。とりあえず納品をゴールとするエンジニアの意識を変える必要がある。複数の開発現場には私が定義したゴールを実直に目指すPLは居ましたが、私が現場の状況を把握するための情報収集する役が必要でした。私が欲しい情報の型を作り、生きた情報で埋めてくれるPMOが存在していたんです。
情報とは①要求マッチ度②進捗度③疲労度(不満・愚痴)④コスト(労務費)⑤不具合/仕様変更でした。
この時すでに組織として成長するための仕組みQMO(Quality Management Office)構想はありましたが、さすがにそこまでする余裕はありませんでした。」
古泉一人ではマネジメントができないから、仕組みでマネジメントを行う必要があるという古泉の実体験から、QMOの概念は芽生え始めていた。
より大きなユーザー利便性を叶えようとすると、1社では賄いきれず連携するための仕様決めが必要となる。業界全体で決めなければならない規格などの標準化活動をする機会も増えていった。
やがてカーナビの国内コンソーシアム幹事を任され、国際標準規格を決める渉外業務に仕事内容も変わっていった。社長の悲願であった国際標準化も通信ナビ分野で韓国・中国等アジア圏を味方につけて一定の成果を残せた。
次に取り組んだのがISO9001の全社取得と実効化として品質保証の仕組みを企画・構築・実行・人材育成の担当をすることになり、QMOの構築に取り組んだ。
またこの時、教育研修を行なってくれていた企業の社長さんからの薦めで日本適合性認定協会(JAB)の公開討論会研究員を3年、WGリーダーも務めた。
そうした製品化現場での作業を経たのち、情報システム部に異動し、社内のルールや仕組みをシステムに落とし込み効率化する活動などを行った。情シスが扱うのは表面的には社内システムであったが、“この会社が社会に対して有用な価値を提供すること”を叶えるために、企業としてどう在りたいかを具現化するのが情シスの役割だと思い、業務に取り組んでいた。
やがて、ファンドによる社長交代や事業の選択と集中をすることが決定して、ここまで来てこの会社での「やり尽くした感」を感じていた古泉はこのタイミングで、24年間勤めたインクリメントPを卒業することを決意して転職活動を開始する。
「自分がフリーランスで仕事をしていた頃、周囲のSES社員達では多重請負などで辛い仕事を経ても人生報われないなと思うことがあったんです。ITゼネコンとかSIガラパゴスとか呼ばれてまして、それらが原因で日本のものづくりを弱体化しているんじゃないかって想いもありました。そして四半世紀を経ての転職活動を通じて改めて業界を見渡してみると、未だにそういう状況は変わってないんだなと感じ愕然としました。」
エンジニアが疲弊する社会構造は正常ではない、なんとかしたいが自分一人で何ができるのだろうと思っていたところ、偶然知ったbravesoftはそのような他の会社とは一線を画した、エンジニア発で世の中を変えたいエネルギーと夢を持って生き生きと挑戦できる会社のように古泉の目には映った。
「独立を考えなくもなかったけど、大きなことを成し遂げたいと思ったんですよね。それには志を一にする仲間が必要。あとは青木CDOの存在は大きかったですね。デザイナーが経営に参画している所も魅力でしたが、何より求めている方向性が合致していたので、入社を決意しました」
この頃の古泉に関して、パートナープロダクト部門を束ねる、青木はこう語る。
「40代のメンバーも少なかったbravesoftから見ると、古泉さんの当時の印象は知識を現場経験を通じて実証して来た真面目な人。いわゆる中身の濃い大人な人という印象があり、何か新しい刺激を与えてくれるんじゃないかという期待感がありましたね。そしてその頃、ちょうど自分が思っていた“プロジェクトチームやメンバーの経験・知識を資産化したい”という課題と古泉さんのやりたいことが合致しており、QMO発足に繋がりました」
そのような青木からの期待もあり、2021年1月、古泉はbravesoftに入社した。

QMSystemに関しての若手社員からの質問にも楽しく応対してくれている
今までなかったQMOの概念を浸透させるのは苦労
そうして2021年1月より、晴れてbravesoftに入社した古泉であったが、入社前思い描いていたイメージと、入社後に実際に目で見た印象をこのように語る。
「思っていた以上に、他の会社と変わらなかったですね(笑)ただマインドは感じた。それが大事!」
古泉の目から見て当時のパートナープロダクトメンバーに優秀なディレクター、優秀なデザイナー、優秀なエンジニアは存在していたが、思っていた以上に「属人的」であり「売り切り根性」で行われており、大鉈を振るう必要があると感じた。
まず古泉は自身でもプロジェクトに参加し、ディレクションも経験してみてこの会社ならではのプロジェクトの進め方や方言・風土を体験することで、この会社にあったQMOの構築を1から始めた。
まず古泉が目を向けたのは、プロジェクトの入り口である“プロジェクト計画書”であった。
このスタート時点で定義するものがプロジェクト憲章になり魂を吹き込むことに繋がるし、お客様とのコミュニケーションが不足していたり、約束事が十分に合意出来ていなければプロジェクトはうまく動かないのは自明の理なので、まずはこのテコ入れから行った。
ポイントはお客様含めたチームビルディングとプロダクトをグロースさせるというワンチーム意識。対価を得て技術を提供しているのだから商契約の相手とは対等にやりあえなければ良いものは作れない。またリリースがゴールと定めがちだが、お客さまにとってはリリースがスタートなのであり、このサービスを持って事業成功できなければ我々も関わった価値はない。
その価値を最大化するために一緒にプロジェクト起点で成し遂げられるプロジェクト憲章にしようと務めた。
次に行ったのは要件定義における定義すべき項目の見直しと、テスト計画・テスト設計に関する取り組み方であった。
これまで40年近くプロジェクトマネジメントを経験してきた古泉の目には、設立して16年のbravesoftのプロダクト開発にはまだまだ自ら考え成長する組織として改善の余地があると考え、そのキーとなるのが要件定義というサービス価値を定めるプロセスと、それが実現できたことを証明する活動であるテスト計画・テスト設計プロセスであった。同じような行為を行なっているようでも、何を目的とし誰とどのような合意を得てプロジェクトを進めるかによって得られる結果や進め方も違ってくる。古泉はこのプロセスが品質や後々のコスト増を抑止する重要なプロセスだと睨んでいた。
こうして入社して半年の2021年8月、苦労しながらも最初の基盤が出来上がったタイミングで、QMOを社内外にアナウンスし価値の浸透を図った。
プレスリリース(2021年8月6日)
トップスピードで突っ込み炎上しがちだったプロジェクトに適度にブレーキを与え、急ハンドルでスピンせず最善のライン取りができるようプロセス標準に軌道修正する機能を持たせるべきだと、次に古泉が取り組んだのが“移行判定”である。
「移行判定は、“お客様含めワンチームでやると決めたことをキチッとできているか”の確認ですね。次の工程に業務を進めるときに、一度立ち止まって、その業務がしっかりできているかの振り返りを行う仕組みになります」
移行判定は、例えば要件定義を終えて、基本設計フェーズに進んだプロジェクトがあるとした場合、次工程の詳細設計フェーズに移る前に、要件定義を行ったスタッフが「自分が決めた要件定義通りに設計に反映されているか」を問いかけ、基本設計スタッフがそれに応え、次工程の詳細設計スタッフが迷いなく取り組める準備が整っているかを確認する行為であり、このように「前工程」「本工程」「後工程」でしっかりと課題認識しどう対処すべきかをなるべく早い段階で行われることがQMSystemを有効に機能させるのに必要不可欠と考えた。
プロジェクトがスピードに乗るとプロジェクトでもドップラー効果が発生しがちになり、周囲の景色は飛んで、目の前の課題・タスクを処理することが全てになってしまう。
世の中は“原因と結果の法則“(≒プロセスによって結果が生まれる)で出来ていて、原因が正されないと悪い結果が繰り返されることになってしまう。
更に、プロジェクトのドップラー効果下では、結果だけを潰して前に進むことが優先され、原因が正されないのが実情であり、同じことを毎回繰り返す成長のない組織に成り果てるケースも往々に存在してしまう。
そして更に、そこに“売り切り根性”が加わるとリリースでフィニッシュしてしまい、原因は忘れ去られ再び同じことが繰り返されてしまい、根源的破滅招来体を潰さなければ、問題と共に無駄なコストは流れ続けてしまうので、移行判定の導入はQMSystemにおいて「必然」であった。
「究極はプロセスの課題を発見するアンテナを立て、皆がタコ部屋に集い濃いコミュニケーションによって都度キャッチアップされるのがベストですが、朝会・夕会といった日毎のキャッチアップが次点、次に移行判定の機会、最低限プロジェクトの最後に振り返りを行なって欲しいと思っています。そうやってキャッチアップした原因分析・改善をプロジェクトの進行に影響を与えず独立して行えるのがQMOの理想的な運用と言えるでしょうね」
このような形で品質を保持する取り組みが良いことであり、意義のあることは全員が理解できた。
しかしながら、これまでは行っていなかった判定を導入することで、単純に作業量が増えるという意識を感覚として持つメンバーも存在したが、それでも古泉は必要性を説き、簡易的に行える工夫も施した。
「もちろん、今までにない事をやろうとしているので、理解してもらえるのに苦労はしました。ですが、やってみて意義は少しずつ浸透してきている状況ですね」
QMSytemにおいて、重要なのはこれまで説明した「品質の水準向上」であるが、同時にもうひとつ「社員スキルの向上」も挙げられる。
要件定義、設計など、各プロセスには経験者同士での選挙から主査が選ばれ、各主査はメンバーの経験協力から最適解を常にアップデートし続け、プロセスの価値最大化に務める。それがチェックシートやテンプレートなどによって言語化・資産化され、あるいは研修資料や研修動画になって、経験の浅いメンバーでも主査と同じ知識を得て業務に就くことができる。
これらを武器・防具として活用できる環境が、若いメンバーの挑戦を奨励し結果を出すことを可能にしているのだ。この挑戦こそが、結果として社員スキルの向上に繋がってくる。
古泉が入社してから半年取り組んだ結果がひとつの成果として結実し、2021年末の社内表彰において、古泉が進めていたQMSystem導入プロジェクトは、bravesoft社内で最も優れていた「Best Project Award」を受賞した。
これからのQMOの課題
そして2022年5月現在、QMSystemは導入から1年が経過し、パートナープロダクト部門において初めから存在していたかのように、当たり前の文化として浸透しつつある。
このように文化が根付いてきたことに対して、青木はこのように語る。
「まだまだ動き出したばかりですが、QMOが自分達で価値を生み出すための装置の様に機能し始めたことを実感しています」
しかしながら古泉の中では、現状はまだ最終的な理想の40%程度の完成度であり、まだまだ残りの60%を埋める必要があると考えている。古泉が実現したいQMOの今後の展望としては、得意を従業員一人ひとりに紐付けること。
「タレントマネジメントの要素を導入したいと考えています。誰が何を得意としているか興味を持っているかを可視化し、活動を評価し、成長を促すことに繋がるようにしたいですね」
タレントマネジメントの導入後も、まだまだ古泉が掲げるQMSystemの野望は果てしない。
山頂は遥か遠く果てしないが、braverと共にならば登れない山ではないと古泉は確信している。
最後に、青木に今後のQMOの展望に関して聞いてみた所、このような答えが返ってきた。
「いまはまだひとつの装置ですが、古泉さんの言葉を借りれば『重力のように』『呼吸をする様』に、自然で有機的なシステムへと進化していくことを期待しています」
最高の品質で、お客様の描くサービスをことごとくグロースさせることが当たり前に可能にすること。
これからも古泉がQMO活動の先頭に立ち、まずはbravesoft全体のレベルアップを実現したあとは、日本中のIT企業にこの仕組みを公開し、多くのIT勇者たちを日本中から量産したい展望を古泉は抱いている。
「このQMOという仕組み自体が“王道”であると私は考えています。それは勇者の行動をbrave spiritsとして標榜するbravesoftだからこそ成し得ること。そしてこの価値観を反映したQMsystemが広く使われ、日本から世界に発信され、世界から勇者が集うだろう。そしてソフトウェアエンジニア発の新しい事業が次々と新時代を築いていく。業界全体に向けて、こういう取り組みは当たり前であるという未来をつくっていくことが、今自分が一番実現したいことですね」

イベンテックにも賛同する古泉。イベントの質をあげて世の中をアップデート!
おすすめの一冊
取材・執筆・推敲 書く人の教科書
このようなタイトルになっているせいで本当に読んで欲しい人に行き渡らないのではないかと思ったので、この本をおすすめします。 この本の本質は「書く人」に的を絞ったものではなく「つくる人」全員が知っておくべきことが書かれています。プロとしてなにかを「つくる人」に共通していえる思考法を伝授してくれる非常に希少価値の高いことが打ち明けられており、また分かりやすく、経験から湧き出るパッションさえ感じる。 大概、本ってなんか偉そうで気取ってて「俺には無理」とか「事情が違う」と思わされながら読まざるを得ないけど、そういうの無く自分でも出来そうに思える、まさに偉業を成したと感動すら覚えた一冊。 読み終えた時、自分もなにか「つくって」「残さねば」と思わせてくれる一冊です。